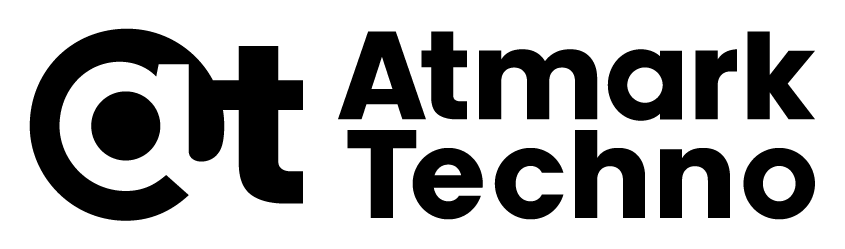開発部 ソフトウェアエンジニア
2019年入社
A.私は小さな頃からモノの中身がどうなっているか調べるのが好きでした。トイレでレバーをひねると、どうして水が流れ、適切なタイミングで止まるのか、ということに疑問を持ち調べたこともあります。
その流れでコンピュータに興味を持ちました。ただ、パソコンはバラしてみても、どのように動いているのかわかりません。そのことがきっかけで余計に興味を持ち、情報電子工学系の学科に進みました。実際に講義を受けていく中でOSなどの比較的下の層のソフトウェアが面白く、情報系のコースを選びました。
A.大学で行われる企業説明会でアットマークテクノを知りました。アプリなどの上の層のソフトウェアに携わる会社が多い中で自社でコンピュータを作り、OSを触れるところが異色だなと感じました。
札幌で働けることと自社製品を持つメーカーであることも理由になり、入社を決めました。
A.新人研修の後は、検査治具を作っていました。当社は出荷前に実際に製造された製品が正しく機能するかを検査しています。その検査をソフトウェアで行います。ソフトウェアを作るんですが、ハードウェアの知識も不可欠な業務なんです。
回路図もインターフェースも理解しないと正しく検査できるソフトウェアを書くことができません。だから、必要な知識を学びながら作っていきました。
A.一番思い出に残っている仕事はAI用のデモを作ったことです。当社のG4という製品のチップにはNPUが搭載されています。「ただNPUが載っている製品を発売するだけでは、お客様はその製品で何を実現できるかわからないよね」という話になり、AIの使い方がわかるデモを作ろうということで私がアサインされました。
NPUでAIを使うためには、作ったAIモデルを最適化する必要があり、その作業が大変でした。今までやってきたソフトウェアのプログラムと全く違ったため、新しい知識を学びながら作りました。全部でデモを10個くらい作り、きちんと動いた時にはとても嬉しかったのを覚えています。ただ、半分くらいはボツになりました。
A.作ったものがきちんと動くときですね。趣味で作るようなソフトウェアであれば、多少おざなりでもいいですが、お客様が使うソフトウェアは予期せぬ使い方をされたときでも不具合が起きないものを作る必要があります。
他のソフトウェアやハードウェアとの兼ね合いも考えなければならないため、あらゆる視点からモノづくりをすることになり、それが楽しく、やりがいを感じます。
A.新しい製品の企画・開発ができる人になりたいです。当社の製品はお客様が開発を加え、量産し、運用するという一連の流れがあります。ソフトウェアはこの開発・量産・運用の使い勝手に直結してくる部分だと考えています。たとえば今、新しいサービスの開発をしているのですが、これはArmadilloがきちんと動作しているかを遠隔で監視するものです。これがあると人手が届かない場所に設置されている機器の運用がとても楽になります。
他にも、開発を進めやすい仕組みや壊れにくい仕組みなど、ソフトウェア次第でお客様に『使い勝手』を提供できるのが、ソフトウェアの良いところだと思います。この遠隔監視サービスの開発では、ベトナムの技術者と共同で作っています。社外の人と開発を進めていくと、すり合わせていく中で足りない部分やケアすべき部分がどんどんと現れてきます。今は、正直その対応で大変ですが、学ぶことが沢山あり刺激になっています。
ソフトウェア業界は新しい知識が次々出てきます。それらをキャッチアップしながら、より便利で使いやすい仕組みをソフトウェアで実現し、よりお客様が使いやすい製品づくりをしていきたいです。
-
9:00 出勤・メールチェック
-
9:30 定常業務
ソフトウェアの設計や実装、ドキュメントの作成など多岐に渡る業務を行います。 -
11:45 ランチ
-
12:45 プロジェクトの会議
プロジェクト単位で進捗管理や相談などを行います。 -
14:00 定常業務
-
15:00 ソフトウェアチームの会議
自社製品に搭載されるソフトウェア全体の方針の決定や、困りごとの相談などを行います。 -
16:00 定常業務
-
18:00 退勤